「このまま経済成長や技術発展をしていってもどうもろくなことがなさそうだ。であれば、いっそのこと伝統農業に根ざした農的自給社会に戻ってしまったらどうか」
本書の主張をかいつまんでいえば、こうなる。昔に戻ればいいことがあるのか。伝統農業でスムーズにすべて物事が解決するのか、と疑問に思われるかもしれないが、それは話が逆だ。伝統農業で解決できた事例だけを集めたのである。
また、プロローグでふれたように、この本に掲載した情報は、すべてインターネット上で得たものだ。現地に出向いての検証作業をしていない。故梅棹忠夫博士は「自分の足で歩いて、自分の目で見て自分の頭で考える、これが大事や」と主張され、『文明の生態史観』も足で発想したと述べている(『梅棹忠夫語る』[日経プレミアム二〇一〇])。ところが、この本は、現地に足を運んでいないうえ、自分の主張に都合がいい情報だけ選り好みしているのだ。それでいて「文明は農業で動く」と題する本を書いてしまっている。いいのか、それで? という批判を受けることを承知のうえで、あえて筆を取ることとしたのには、二つのわけがある。
ひとつは、近代農業があまりにも要素還元主義的になっていることだ。『医道の日本』という雑誌の座談会(二〇一〇年一〇月号)で鍼灸等の伝統医療や有機農業について千葉大学の広井良典教授と対談する機会があったが、その際、次の言葉が筆者の耳には強く残った。
「伝統に回帰するか、近代科学を推進するかは二者択一ではない。『複雑系』もそのひとつだ。今は科学そのものがホーリスティックな方向に向かっている」
広井教授は著作『コミュニティを問いなおす』(ちくま新書二〇〇九)で、細菌だけに病因を求める要素還元主義的な近代医学は、「感染症と戦争」への対応から誕生したもので、今後の医療は複雑系として「病」を捉え、コミュニティの中でケアをしていくことが欠かせないと主張されている。この分析は、まさに農業とも重なる。近代農業は、第一次大戦中の火薬と毒ガスをベースに開発された化学肥料と農薬から誕生した。養分不足には化学肥料、害虫対策には農薬と、これもまた要素還元主義的な対応で、それが緑の革命の失敗を招いた。例えば、インドネシアで緑の革命後の害虫問題に直面したFAOのピーター・ケンモア博士は、こう語っている。
「水田に農薬を散布すると、なんと五〇〇~一〇〇〇倍も害虫が増えたのです。最初になされた対応策は農薬をさらに散布することでしたが、それはさらに問題を悪化させました。一九六八年に、フィリピン政府は、ハーバード・ビジネス・スクールにアドバイスを求めますが、さらに資材を投下するという不完全な科学に基づく古典的なメソッドしか得られませんでした。そして、抵抗性品種を育成しましたが、それでも駄目でした」
では、なぜ農薬を撒くと害虫が増えるのか。博士は二種類の虫がいることに着目しなければならないと指摘する。
「コメを食べる虫と、コメを食べる虫を食べる虫がいます。ですが、農薬を散布すると、コメの中に潜んでいる害虫の卵を除き、両方とも殺してしまいます。そこで、害虫が孵化すると天敵がいないため、爆発的に増えるのです。もちろん、害虫発生は直ちには起こらず、四、五年はかかりますが、高収量米品種が一九六六年、六七年に導入されると、一九七〇年前後に最初に大発生し、その後ずっと南アジアと東南アジアでこの問題が続くこととなるのです」
では、緑の革命以前にはなぜ害虫は発生しなかったのだろうか。ケンモア博士はこう続ける。
「現在もそうですが、過去四○○○~五○○○年、それ以外のどの植物よりもコメはホモサピエンスを養ってきました。歴史家ヒュー・トーマスは『もし過去一万年を一言で語れば、それは稲作の時代だ』と述べています。過去一万年、多くの人々は、それ以外のどの仕事よりも稲作に取り組んだのです。つまり、昆虫と稲と人間は五〇〇〇年も『共進化』してきました。熱帯地方では一年に虫は一〇世代も誕生しますから、五万世代です。物凄い量の共進化です。ですから、ほとんどの熱帯諸国では一九六〇年代までは無農薬で栽培されてきたのです」(1)
とはいえ、ケンモア博士に批判された不完全な科学も、その後は発展し、「共進化」にも取り組んでいくこととなる。そのひとつが、一九八四年に設立されたサンタ・フェ研究所が中心となって発展した複雑系の科学だ。バリの灌漑で紹介したランシング博士は「その後、我々は『秩序の起源』でカウフマンが提起した疑問を追求した」と述べている(2)。カウフマンとは、サンタ・フェ研究所の看板研究者スチュアート・カウフマンのことで、スピルバーグ監督の映画『ジュラシック・パーク』に登場するジェフ・ゴールドブラム演じるカオス理論の科学者イアン・マルコム博士のモデルにもなった人物である(3,4)。
最先端の科学である複雑系が、伝統農業ともリンクする。これは筆者には意外な驚きだった。広井教授の指摘のように、医療が、伝統医学も統合した複雑系としてのケアへと進化していくとなれば、農業も伝統農業を統合した複雑系としてのアグロエコロジーに進化していかなければならないだろうし、その際、キーワードとなるのは、医療と同じくコミュニティであろう。
ちなみに、医療やケアでは「レジリアンス(回復力)」という概念が着目されているが、気候変動等グローバルな環境問題に対していかに社会がリスク対応するかでも「レジリアンス」が着目されている。スウェーデン王立科学アカデミー・ベイエ生態経済学国際研究所やストックホルム大学のストックホルム・レジリアンス・センターのカール・フォルケ教授が代表的な研究者のひとりだが、彼らが着目しているのも、リスク回避や回復力に富んだ伝統社会の生態系管理と社会規範の叡智なのだ(5)。
二つ目は、二〇一〇年九月八~一三日に生まれて初めて筆者は韓国を旅したが、その際、韓国の出版社から「伝統農業について本を執筆して欲しい」との依頼を受けたことだ。
意外に思われるかもしれないが、韓国は有機農業先進国である。元農林水産省政策研究所の足立恭一郎博士やジャーナリストの青山浩子氏が詳細にリポートしているが、「環境農業育成法」が制定されたのは一九九七年一二月と日本より一〇年早く、認証農産物の国産シェア率も日本の〇・一九(二〇〇九年)に比べ一一・九パーセント(二〇〇九年)と格段に多い。この取組みは国際的にも認められ、二〇一一年には国際有機農業運動連盟の大会が初めてアジアで開かれるが、その開催国として選ばれたのも韓国である。
この有機農業を推進したキーマンが、金成勲(キム・ソンフン)元大臣で、同元大臣の講演会が開催されるというので、NGO「帰農運動本部」を訪ねてみた。帰農運動本部とは、農村人口の減少への危機感と都市住民への農業の認知を図るため、一九九六年に設立された団体である。ソウル市内から電車で四〇分。京幾道軍浦市内の築三〇〇年の文化財にもなっている伝統家屋を改造した本部の周囲には日本と瓜二つの水田や里山が広がる。本部は、世界各地の有機農業や持続可能な農法の情報収集に熱心なだけでなく、国内に眠る伝統農法の収集や保全にも取り組んでいる。そのひとつがスリランカと同じ歳時記の重視だ。韓国の伝統農業は、日本と同じく、春分、夏至、秋分、冬至と月や星の運行によって一年を二四区分し、この「節気」に基づき作付けを行ってきたが、それに基づく在来品種の栽培実験に取組んでいる。伝統衣装に身を固めた鄭?秀(ゾン・ヨンース)本部長の案内で、実験田を訪れると、折しも九月七日に襲来した台風九号の影響で周囲の慣行農法の稲はことごとく倒伏していたが、本部の無農薬・無化学肥料の伝統稲作田のみが青々と茂っていた。
収量は必ずしも高いとは言えず、反収は五〇〇キロにすぎない。このため、伝統農法では食料自給や食料安全保障が確保できないとの批判の声もあると言う。とはいえ、同本部の安?煥(アン・チォルファン)氏は、収量よりもリスク削減にこそ伝統農法の本来の目的があると主張する。安氏は五年前から伝統農業の復興に取組み始め、現在、都市農業委員会委員長として、都市農業と伝統農業とをどう結び付けるかに尽力しているのだが、氏の見解は本書の中で述べた他国の伝統農業の見解とも重なる。そして、講演会場となった本部付属農場のハウスに元大臣とともに現れたのは、本部長と同じく伝統衣装に身を包んだ安完植(ワン・シク・アン)博士だったが、同博士の活動が在来品種の保存につながったという。
「私は日本に留学しあなたが学ばれた筑波大学で学位を取得した後、ノーマン・ボーローグ博士の研究室で働いていたのです」
キューバのみならず、有機農業では日本に一歩先んじている韓国においても、なおかつ、緑の革命の総本山で働いてきた研究者が、次のステップとして伝統農業に着目している。これも意外な発見だった。
こうして、インターネット上での情報収集を始めることとなったが、整理するにあたって、著者なりに工夫はした。ひとつは、欧米の先進事例については、日本語で多くの既存書物が出ているため、情報の棲み分けを図る意味で、これを一切省き開発途上国に絞った。例えば、農業発達史を見れば、イギリスのジェスロ・タルが一七〇八年に「種子ドリル」を発明し、それが農業発展に寄与したとの話は教科書を読めばたいがい出ている。とはいえ、紀元前四〇〇年のインドの「クリシ・パラシャーラ」にすでに、ディスク・プラウ、木製のスパイクハロー、種子ドリル等の農機具が解説されていることを指摘している本は少ないのではないだろか。少なくとも私はインドのウェブサイトを見るまで知らなかった(6)。
二つ目は、開発途上国の事例であっても、すでに日本語で読める情報は極力省いた。例えば、伝統農法による地域再生事例として英文上でも必ずヒットするのは、サハラの「ザイ農法」だが、これは『アフリカ農業と地球環境―持続的な農業・農村開発はいかに可能か』家の光(2008)で紹介されている。ジャワのアグロフォレストリー「クブン・タルン」も有名だがすでに多くの書物や論文で紹介され、フィリピンのコルディエラ山地の棚田も大崎正治氏の著作「フィリピン・ボントク村」農文協(1987)がすでに出ている。アジアの紹介事例が量的に少なくなったのはそのためだ。
三つ目には、無化学肥料・無農薬でどうやって食料を確保するのか、という視点から、持続可能な農業の「伝統技術」に軸を据えた。ラテンアメリカやインド、スリランカについては数多くの現地リポートが出ているが、民俗学や文化人類学とは違う切り口で描いたことで、重なりが避けられたのではないかと思っている。
四つ目は、持続可能な農法であっても、伝統農業と無関係の取り組みは一切省いた。例えば、アジアの水田稲作ではSRIが欠かせないし、農民参加型の育種や農民圃場の学校の動きも重要だが、これらは伝統農業とは直接関係ないために除いた。
また、日本の有機農業や伝統農業についても、一切ふれていないが、これにもわけがある。伝統農業についてネットで調べはじめ、筆者がまず遭遇したのは次のような記事だった。
「スリランカの伝統的な農民たちは、渡り鳥、インドヤイロチョウの鳴き声を耳にするまで田植えの準備を始めない。愚かな迷信とも思える。だが、今ではその理由が明らかになっている。インドヤイロチョウは、飛翔力があまりない。だから、九月に吹き始める北東モンスーンの風に乗ってインドから飛来する。このモンスーンが、稲作に欠かせない恵の雨をスリランカの大地にもたらす。風が吹くまで移動できない渡り鳥。農民たちが鳥を待つことには意味があったのだ」(7)
風土と一体となった農法の奥深さを紹介する一九八三年のエコロジスト誌に掲載されたこの記事を読んだとき、三〇年近くも前のある秋の日に、研修先の農家で耳にした次のフレーズが記憶の底から蘇った。
「山の紅葉が本当にきれいですね」
「昔は、あの山に赤毛の馬を放していてね、その毛色が山と見分けがつかなくなったときに○○をしたものですよ」
その老人は「コブシの花が咲くときに○○を植えよ」といった地域に伝承されてきた農の歳時記を教えてくれたのだった。積算温度や降雨量が毎年微妙に変化することを考えれば、県の普及センターや試験場が作成した栽培暦よりも、この風土に溶け込んだ生物指標の方がはるかに正確なことは間違いない。
実は、この老人は、日本を代表する有機農家で筆者の師匠にもあたる金子美登氏の御尊父、故万蔵氏である。金子美登氏は「小利大安」、すなわち、「小さな利益で、大きな安心」というスローガンを提唱されているが、その指摘は、前述した安?煥氏の発言とも重なり、本書で描いた伝統農業に共通するリスク削減の哲学とまさに同じである。
「有機農業」は、とかく無農薬・無化学肥料で堆肥を投入するだけの農法や高付加価値化のためのニッチ・ビジネスと捉えられがちだが、以前から有機農業に取り組んできた金子氏に代表されるパイオニア的農家の哲学は、本書の中で紹介してきたアグロエコロジーや伝統農業の思想と響き合う奥深さを持つ。金子氏の農法も三〇〇年に及ぶ星霜を経た伝統のうえに立脚しているからだ。すなわち、日本農法についても、すでに篤農家の良書があるわけで、それを読めばよい。
とはいえ、他国の例を知ることも無駄ではない。広く浅く世界各地の取り組みを概観しておくことは、自分たちの実践がどこに位置しているのかの羅針盤として役立つ。コラムで紹介した複雑系(レジリアンス)の目線で伝統農業が持つ意義を再確認することも、生産効率や経済性という狭い枠組みで農業を捉える罠に陥る危険性を避けられる。ところが、伝統農業に関心が深い韓国においても、国内事例はともかく、ラテンアメリカやインド、アジアを横断的に整理し、複雑系の切り口で照射した書物はないという。それが、筆者に執筆を依頼してきた理由なのであった。
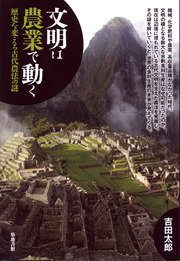
書名:文明は農業で動く
著者:吉田太郎[著]
発売日:築地書館
2011年4月15日