本の魅力は、著者の人生歴によるところが大きい。だいたいが、人とは違う人生を意図せずとも歩んでいる。
この本の著者、大野拓司さんの人生もかなり個性的なものだ。本ではほとんど触れられていないが、理解の手助けに少し紹介しておこう。
東京・奥多摩町の生まれ。慶応大学を卒業後、アルバイトで貯めた300ドルを懐に横浜から貨物船に乗ってマニラへ。「いわばモラトリアムで1年くらいブラブラしたい。熱帯フィリピンなら安く暮らせそう」が渡航動機というのだから、愉快な人だ。
1年いるためにはビザが必要で学生になるのがいい、と言われ、国立フィリピン大学の大学院に籍を置く。「暑い、汚い、危ない国だったけど、緩い、やさしい、深い人たち」にどっぷりとはまり、ズルズルと遊学すること7年。その間、日本からやって来た小野田少尉捜索隊の案内や通訳など、数々のアルバイトで生活費を捻出した。
気がつけば、30歳が目前。まともな就職先の当てもなく焦りがなかったといえば噓になるが、人生ケセラセラ。なにが幸いするか分からない。こんな経歴が買われて朝日新聞に入社。外報部などで記者として活躍し、1991年から3年ほど待望のマニラ支局長を務めた。
この本は、マニラで発行されている邦字紙『日刊まにら新聞』に執筆した連載記事がもとになっている。2021年のマゼラン船団フィリピン到達500周年に合わせた企画で、大幅に加筆して2023年11月に出版された。
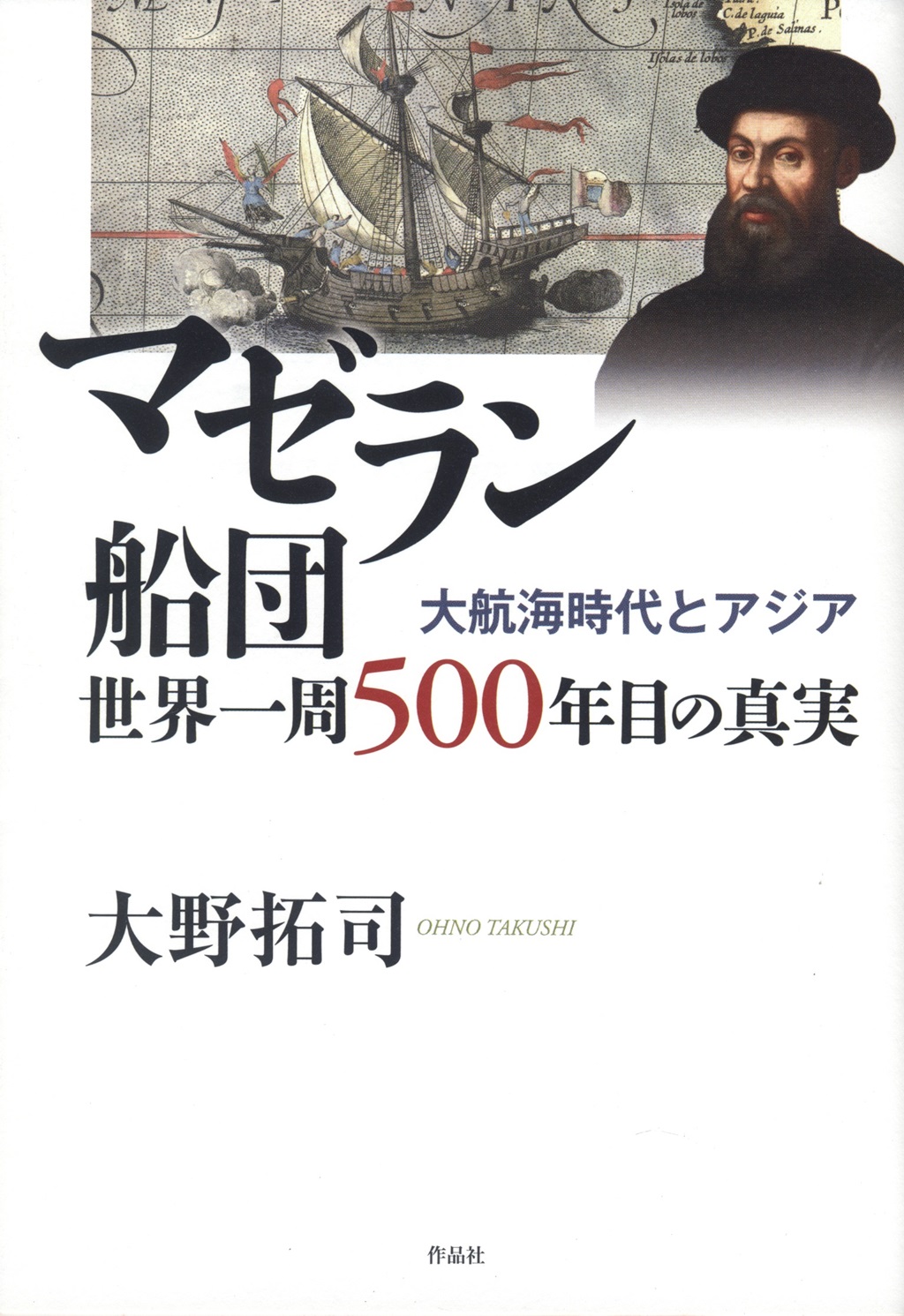
承知のように、マゼランは初めて世界一周の航海に成功した遠征隊の総指揮官として歴史に名を残す。遠征隊は1519年9月にスペインを出港し、地球を西回りで大西洋、太平洋、インド洋と進み、3年後に一部が帰還。目的は海外領土の拡大と香辛料(スパイス)の獲得だったが、当のマゼランは途次のフィリピン中部の小島での戦闘で戦死している。
執筆の狙いは、ため息のように文中で漏れてくる、大野さんのこんな反発で明らかだ。
「ヨーロッパ史が世界史なのか」
そして、こんな言葉が記される。
「フィリピンは『野蛮』でも『未開』でもなかった」
マゼランらが登場した15~17世紀は、コロンブスのアメリカ大陸、バスコ・ダ・ガマのインド航路など「大発見時代」と世界史的に喧伝されてきた。しかし、それは西洋の視点であり、今では「大航海時代」との言い換えが進んでいるようだが、「ヨーロッパ史こそ世界史」との意識は根強い。私もこの本を開くまで、フィリピンをはじめ東南アジアの国々を西洋の歴史認識に染まったまま眺めていたことに気づかされ、反省した。
「『発見された側』からすれば『大虐殺の時代』であり、『大略奪の時代』でもあった」
マゼラン後、植民地として300年を超える歴史や庶民の暮らしの裏事情までを、書斎の知識ではなく現場感覚で知り尽くす大野さんだからこそ、この指摘には全体重をかけた説得力がある。
とまあ、こんな風に紹介していけば、なにやら頭の固い書物の印象を与えかねない。が、そこは文章と取材に長けたジャーナリストである。
本の半分を占めるのは、残された当時の文献・資料を駆使し、世界一周の初航跡をノンフィクション仕立てに再現するのに費やされ、読み物として十分楽しめる。武装集団だったマゼランが殺害される幾重もの誘因を、地元住民の視点を交錯させ、まるで社会派ミステリーを読んでいくようで興味深い。
一方で、かなりのページを割き、マゼラン前のフィリピン諸島に光を当てる。セブ島には南シナ海沿岸から多くの船が出入りし、ルソン島では古代インド系の文字「バイバイン」が存在した。高床式の家が並び、バナナやパパイアがたわわに実る、穏やかで慎ましい暮らしぶりに言及する。
エピソードにも事欠かない。「黄金の国ジパング=日本」説に首を傾げ、「ジパングはフィリピン」とする学者の有力な論文を取り上げる。
近年、セブ島に英語学校が続々と誕生し、日本の若者の語学留学が増えていると聞く。フィリピンの歴史や政治、宗教、経済、地理、気質、肌や髪の色、食習慣、トイレ事情に至るまで随所に書き込まれたこの本が、彼らの必読書となる日がやって来るかもしれない。
■大野拓司さんプロフィール
おおの・たくし/ジャーナリスト。1948年生まれ。元朝日新聞記者で社会部を経て、マニラ、ナイロビ、シドニーの各支局長を務めた。『朝日ジャーナル』旧ソ連東欧移動特派員、『アエラ』副編集長などにも就く。現在、米ニューヨーク・タイムズが配信する記事を選んで訳出し、朝日新聞デジタル『Globe+』に『ニューヨーク・タイムズ世界の話題』として連載している。『北朝鮮からの亡命者60人の証言』(編著)『飢えるアフリカ』(共著)など著書多数。
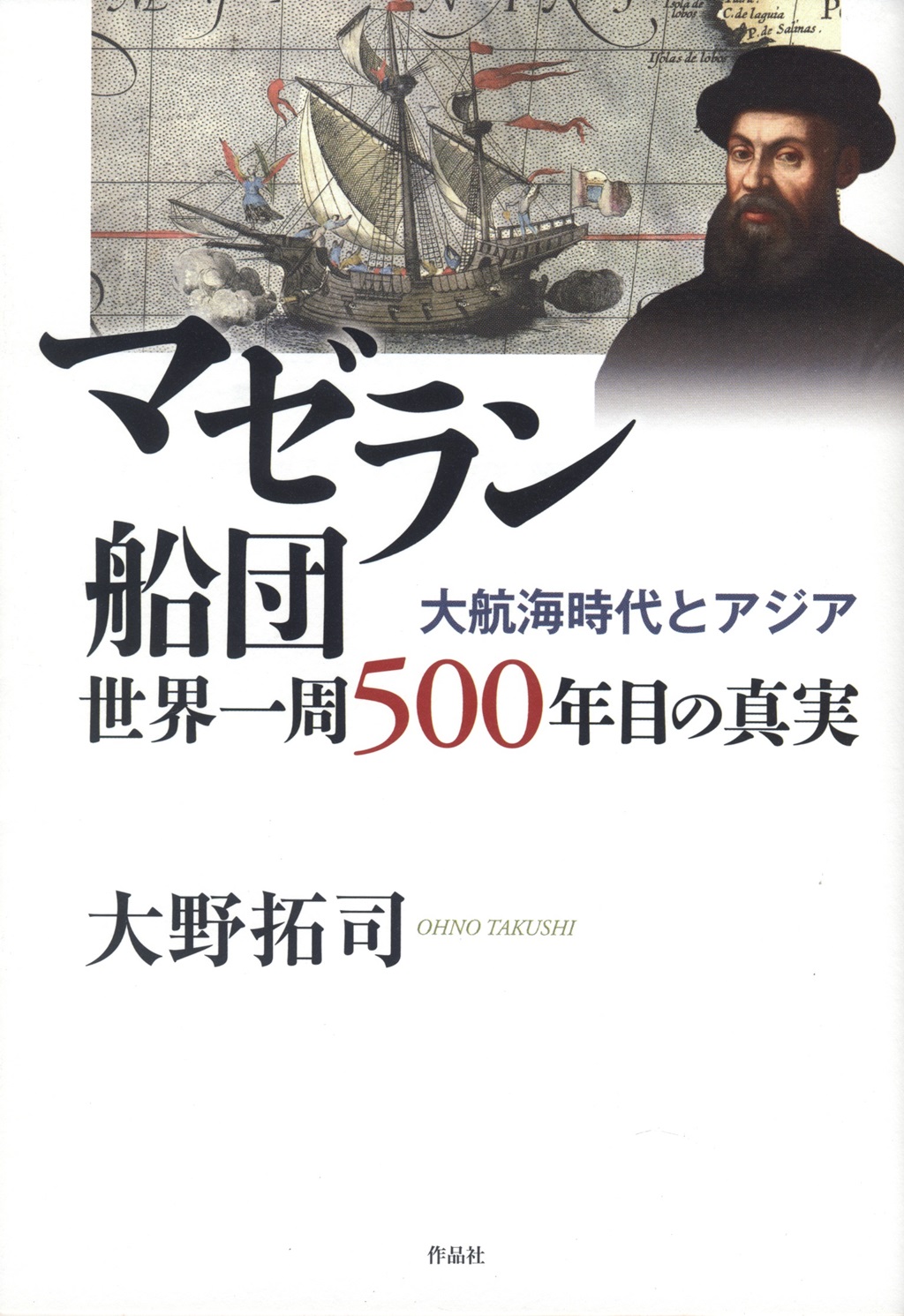
当サイトご覧の皆様!
おすすめの本を教えてください。
本のリクエスト承ります!
広告掲載をお考えの皆様!
BOOKウォッチで
「ホン」「モノ」「コト」の
PRしてみませんか?